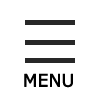【ブックFOREVER #1】追悼 中山均
[ブックFOREVER] 2016年05月28日
ブックソムリエ鍋島の高校の同級生の遺作を紹介させてください。
★★
ブックソムリエの鍋島です。
「ブックFOREVER」と題して本への愛を週1回の定期(しばしば不定期)にお届けいたします。
ブックソムリエの鍋島です。
「ブックFOREVER」と題して本への愛を週1回の定期(しばしば不定期)にお届けいたします。
今回はこのブログを始めるきっかけとなった1冊の本を紹介させてください。
★★
もしも13歳の子どもが川端康成なみの言語能力を持っていたら、みずからにふりかかるいじめをどのような言葉で表現するだろうか?
それを知りたい人は中山均のこの作品を読んでみてください。おどろくべきみずみずしい感性を卓抜した言語で表現する私小説群です。
その作品は2016年4月に発刊された『菜園・戴冠式』(アルファベータブックス)。OBPアカデミアの雑誌コーナーの右横の棚に展示していますので、ぜひ手にお取りください。「中山均初期作品集」というサブタイトルが示すように、彼が1980年代に16歳から22歳という若き日々に執筆した5本の短編小説が所収されています。このうち冒頭の作品「オレンジロード」は彼が16歳の時に高校生向けの雑誌で入選した作品、本書のタイトルともなっている「菜園」は東大で銀杏並木賞を受賞した作品。そして3編目の「入江橋」は知る人ぞ知る『三田文学』に掲載された作品です。
三田文学は森鴎外、永井荷風、芥川龍之介らを輩出した1910年創刊の日本で最も歴史ある文学同人誌のひとつです。今も発行されていますが、この雑誌は創刊以来7度の休刊を強いられた歴史があって、そのたびに苦難を乗り越えて8度の復刊を果たしてきました。文字通り七転び八起きです。
三田文学が10年近いブランクを経て8度目の復刊をはたしたのが1985年です。その記念すべき復刊第1号は、戦後初期の作家についての井伏鱒二と安岡章太郎の対談からはじまり、吉行淳之介、遠藤周作などの錚々たる作家が寄稿しています。その中に「新人」として中山均の名前が見えます。22歳。鮮やかな文壇デビューと言っていいでしょう。まちがいなく天才だったと思います。

彼の作品はいわゆる私小説です。私小説というのはこういう書評を書くときは実に厄介なもので、ミステリーやアドベンチャーのようなわかりよい「筋書き」を欠いているものが多いですね。その代表的なものと言えば志賀直哉の「城の崎にて」でしょうか。筋書きとしては「おっさんがじっとイモリを見つめている話し」なんですが、こう書いても読者は「???」ですね。このおっさんがイモリをみながら延々と心のつぶやきを発するところが味噌なのですが、これをちゃんと紹介した「書評」を私はあまりみたことがありません。無理にストーリーらしきものをこじつけた紹介はかえって作品の本質を台無しにする、というような書評がものすごく多いですね。
そういうわけで、中山均の小説をあらすじで紹介するのは困難なのですが、いちおうやってみましょう。
「オレンジロード」・・夏休みの終わりに16歳の少年が1歳年上の従姉を駅まで送っていく話し。
「菜園」・・23歳と1歳の父子家庭の親子が家庭菜園を耕す話し。
「入江橋」・・病気で入院していた男が久しぶりに家に帰る話し。
「赤い樹」・・大学生の青年の下宿へ、やんちゃして家出した中学生の弟が彼女を連れてやってくる話し。
「戴冠式」・・自分の兄に惚れている家庭教師のお姉さんがちゃんと勉強を教えず兄のアルバムを覗き見するはなし。
おいおい、なんのこっちゃ、ですよね。盛り上がりそうにもないこんな小説を誰が読むねんという話しですが、私小説はそれが面白いところなのです。
このように筋書きを挙げると中山が一貫して「家族」をテーマにしているのではないかと見えますが、全然違います。筋書きやキャスティングは彼の作品のなかで重要な役割を果たしていますが、しかし彼の描写はそれを超える「なにか」に向けられていきます。彼自身はそれを「やさしさみたいなもの」と言っています。
また私小説ですから作者自身の状況が語られているのではないかと思う人もいるでしょうが、私の知る限りどの登場人物も中山本人の性格や状況とかぶるものはいません。おそらく彼は入念に人物設定を行なって自らの作品を構成したものと思われます。
私自身が彼の作品に共感するところはといえば、主人公たちの強い一方的な思い入れと、それに釣り合わない臆病さでしょうか。なにかに強い思い入れを抱きながら、アクションをおこすことを避ける。アクションに移すことのできる強いメンタリティを否定する。挙句の果てにそのような「繊細なやさしさ」を察しない相手の鈍さを恨む。ヒロイズムとは無縁な、中山特有の人物がなんとなくいとおしく感じます。
ところで先日Yahooニューズに村上春樹を英語に翻訳した人の記事がありました。曰く、「村上をグローバル作家にしたのは、私小説に代表される日本独特の美しい文体と暗い内面描写を捨て、シンプルで明るいアメリカ文学のスタイルを採用したから」だそうです。なるほど、と思う反面、やはり私小説は時代に合わないのかなと少し寂しく思いました。中山の作品も美しく、そして暗い。私は日本の私小説にはオリジナルな美しさがあると思っています。中山の作品でその美しさをぜひご堪能ください。
■私的なことですが・・
中山均は私の高校の同級生です。高校時代、私たちにとって書くことが日課でした。熱く文学や美について語り合った日々を懐かしく思い出します。そして彼の作品の美しさは、もはやライバル意識や妬みも感じさせない、異次元の領域でした。彼の文体に近づこうと彼が読んでいるものを読み、書こうとすることに関心を持とうとしました。ノンフィクションを好んで読んだ私が大江健三郎、阿部公房、筒井康隆といった作家たちに傾倒し、中原中也や萩原朔太郎をはじめとする近代詩の世界に浸かることになります。私は高校卒業後に文学部へ進学し美学を学ぶこととなりましたが、中山との出会いがなけれはそのような進路選択はなかったと思います。彼の文学は、私の人生に深く刻み込まれています。
中山はというと、凡庸な私とちがってあらゆる分野でよくできる生徒でしたから、「数学は美しい」と言って東大の理学部に進学し、数学科を卒業しています。そして三田文学で作家デビューとつながっていきます。
ただ少し驚きだったのは、彼がテレビ局に就職し、ジャーナリストになったことです。国会議事堂の前や、ロシアの赤の広場でカメラの前に立つ彼の姿を見たのは90年ごろでしょうか。友人の結婚式で会ったときには、まだ世間に知られていなかったオウム真理教のことを詳しく教えてくれました。しかしほどなく彼の姿はカメラの前からも、私たち同級生の前からもぷっつりと消えてしまいました。
それから四半世紀がたち、2015年の夏。再開された音信は、友が余命2年であるという知らせでした。
死にゆく友との電子文通がはじまります。
鍋島祥郎様
中山です。昭和以来ではないでしょうか。
私この春、激辛食好みの祟りか食道癌ステージⅢを宣告され、「がん研有明病院」で食道を全摘出、現在埼玉の自宅で療養中です。
(中略)
私、あと2年ほどは寿命があるように思います。この際貴君と様々なテーマでお話をしたいのですが、遠方ゆえ面会も容易と思えません。今は咳き込むので会話も不自由です。またメールいただければ幸いです。まずは、ご連絡のお礼まで。
このメールを見て、わたしはすぐに東京のがん研へ見舞いに行きました。
がらんとした巨大病院の1階コンビニ前で待ち合わせた私たちは、「昭和以来」の再開にしばし呆然と互いに見つめあいました。
昔と変わらないぱっちりとした彼の目から涙が数滴。
ジャーナリストとしての挫折。彼の人生に働いた強い重力。その果てにがんの発症。
「なんで俺は作家になれなかったのだろう。」そのつぶやきに彼の疲れが凝縮されていました。
それから半年、この5月1日に友はこの世を去りました。
そしてこの世を去る前に遺した1冊の本。それがこの『菜園・戴冠式』です。
印刷が完了して書店の店頭に出たのが4月20日。
暖かい友人たちが、最速で本を買い、読み、感想を届けてくれました。
それを彼に転送しました。
「旧友の反応ありがとうございます。励みになります。緩和病棟が緩和されないので出てきました。酒飲んでもいい病棟でしたが病院で飲む酒の不味いこと。自宅ベッドで末期がん患者らしく横たわっています。まさか自分にこの境遇が来るとは、思いもよりませんでした。 中山 均」
それから10日後、彼の死の知らせを受け取りました。
作家として死にたい。それが彼の最後の望みだったのだと思います。
私も書き続けることを決意しました。
中山均君のご冥福をお祈りいたします。
了
★★
もしも13歳の子どもが川端康成なみの言語能力を持っていたら、みずからにふりかかるいじめをどのような言葉で表現するだろうか?
それを知りたい人は中山均のこの作品を読んでみてください。おどろくべきみずみずしい感性を卓抜した言語で表現する私小説群です。
その作品は2016年4月に発刊された『菜園・戴冠式』(アルファベータブックス)。OBPアカデミアの雑誌コーナーの右横の棚に展示していますので、ぜひ手にお取りください。「中山均初期作品集」というサブタイトルが示すように、彼が1980年代に16歳から22歳という若き日々に執筆した5本の短編小説が所収されています。このうち冒頭の作品「オレンジロード」は彼が16歳の時に高校生向けの雑誌で入選した作品、本書のタイトルともなっている「菜園」は東大で銀杏並木賞を受賞した作品。そして3編目の「入江橋」は知る人ぞ知る『三田文学』に掲載された作品です。
三田文学は森鴎外、永井荷風、芥川龍之介らを輩出した1910年創刊の日本で最も歴史ある文学同人誌のひとつです。今も発行されていますが、この雑誌は創刊以来7度の休刊を強いられた歴史があって、そのたびに苦難を乗り越えて8度の復刊を果たしてきました。文字通り七転び八起きです。
三田文学が10年近いブランクを経て8度目の復刊をはたしたのが1985年です。その記念すべき復刊第1号は、戦後初期の作家についての井伏鱒二と安岡章太郎の対談からはじまり、吉行淳之介、遠藤周作などの錚々たる作家が寄稿しています。その中に「新人」として中山均の名前が見えます。22歳。鮮やかな文壇デビューと言っていいでしょう。まちがいなく天才だったと思います。

彼の作品はいわゆる私小説です。私小説というのはこういう書評を書くときは実に厄介なもので、ミステリーやアドベンチャーのようなわかりよい「筋書き」を欠いているものが多いですね。その代表的なものと言えば志賀直哉の「城の崎にて」でしょうか。筋書きとしては「おっさんがじっとイモリを見つめている話し」なんですが、こう書いても読者は「???」ですね。このおっさんがイモリをみながら延々と心のつぶやきを発するところが味噌なのですが、これをちゃんと紹介した「書評」を私はあまりみたことがありません。無理にストーリーらしきものをこじつけた紹介はかえって作品の本質を台無しにする、というような書評がものすごく多いですね。
そういうわけで、中山均の小説をあらすじで紹介するのは困難なのですが、いちおうやってみましょう。
「オレンジロード」・・夏休みの終わりに16歳の少年が1歳年上の従姉を駅まで送っていく話し。
「菜園」・・23歳と1歳の父子家庭の親子が家庭菜園を耕す話し。
「入江橋」・・病気で入院していた男が久しぶりに家に帰る話し。
「赤い樹」・・大学生の青年の下宿へ、やんちゃして家出した中学生の弟が彼女を連れてやってくる話し。
「戴冠式」・・自分の兄に惚れている家庭教師のお姉さんがちゃんと勉強を教えず兄のアルバムを覗き見するはなし。
おいおい、なんのこっちゃ、ですよね。盛り上がりそうにもないこんな小説を誰が読むねんという話しですが、私小説はそれが面白いところなのです。
このように筋書きを挙げると中山が一貫して「家族」をテーマにしているのではないかと見えますが、全然違います。筋書きやキャスティングは彼の作品のなかで重要な役割を果たしていますが、しかし彼の描写はそれを超える「なにか」に向けられていきます。彼自身はそれを「やさしさみたいなもの」と言っています。
また私小説ですから作者自身の状況が語られているのではないかと思う人もいるでしょうが、私の知る限りどの登場人物も中山本人の性格や状況とかぶるものはいません。おそらく彼は入念に人物設定を行なって自らの作品を構成したものと思われます。
私自身が彼の作品に共感するところはといえば、主人公たちの強い一方的な思い入れと、それに釣り合わない臆病さでしょうか。なにかに強い思い入れを抱きながら、アクションをおこすことを避ける。アクションに移すことのできる強いメンタリティを否定する。挙句の果てにそのような「繊細なやさしさ」を察しない相手の鈍さを恨む。ヒロイズムとは無縁な、中山特有の人物がなんとなくいとおしく感じます。
ところで先日Yahooニューズに村上春樹を英語に翻訳した人の記事がありました。曰く、「村上をグローバル作家にしたのは、私小説に代表される日本独特の美しい文体と暗い内面描写を捨て、シンプルで明るいアメリカ文学のスタイルを採用したから」だそうです。なるほど、と思う反面、やはり私小説は時代に合わないのかなと少し寂しく思いました。中山の作品も美しく、そして暗い。私は日本の私小説にはオリジナルな美しさがあると思っています。中山の作品でその美しさをぜひご堪能ください。
■私的なことですが・・
中山均は私の高校の同級生です。高校時代、私たちにとって書くことが日課でした。熱く文学や美について語り合った日々を懐かしく思い出します。そして彼の作品の美しさは、もはやライバル意識や妬みも感じさせない、異次元の領域でした。彼の文体に近づこうと彼が読んでいるものを読み、書こうとすることに関心を持とうとしました。ノンフィクションを好んで読んだ私が大江健三郎、阿部公房、筒井康隆といった作家たちに傾倒し、中原中也や萩原朔太郎をはじめとする近代詩の世界に浸かることになります。私は高校卒業後に文学部へ進学し美学を学ぶこととなりましたが、中山との出会いがなけれはそのような進路選択はなかったと思います。彼の文学は、私の人生に深く刻み込まれています。
中山はというと、凡庸な私とちがってあらゆる分野でよくできる生徒でしたから、「数学は美しい」と言って東大の理学部に進学し、数学科を卒業しています。そして三田文学で作家デビューとつながっていきます。
ただ少し驚きだったのは、彼がテレビ局に就職し、ジャーナリストになったことです。国会議事堂の前や、ロシアの赤の広場でカメラの前に立つ彼の姿を見たのは90年ごろでしょうか。友人の結婚式で会ったときには、まだ世間に知られていなかったオウム真理教のことを詳しく教えてくれました。しかしほどなく彼の姿はカメラの前からも、私たち同級生の前からもぷっつりと消えてしまいました。
それから四半世紀がたち、2015年の夏。再開された音信は、友が余命2年であるという知らせでした。
死にゆく友との電子文通がはじまります。
鍋島祥郎様
中山です。昭和以来ではないでしょうか。
私この春、激辛食好みの祟りか食道癌ステージⅢを宣告され、「がん研有明病院」で食道を全摘出、現在埼玉の自宅で療養中です。
(中略)
私、あと2年ほどは寿命があるように思います。この際貴君と様々なテーマでお話をしたいのですが、遠方ゆえ面会も容易と思えません。今は咳き込むので会話も不自由です。またメールいただければ幸いです。まずは、ご連絡のお礼まで。
このメールを見て、わたしはすぐに東京のがん研へ見舞いに行きました。
がらんとした巨大病院の1階コンビニ前で待ち合わせた私たちは、「昭和以来」の再開にしばし呆然と互いに見つめあいました。
昔と変わらないぱっちりとした彼の目から涙が数滴。
ジャーナリストとしての挫折。彼の人生に働いた強い重力。その果てにがんの発症。
「なんで俺は作家になれなかったのだろう。」そのつぶやきに彼の疲れが凝縮されていました。
それから半年、この5月1日に友はこの世を去りました。
そしてこの世を去る前に遺した1冊の本。それがこの『菜園・戴冠式』です。
印刷が完了して書店の店頭に出たのが4月20日。
暖かい友人たちが、最速で本を買い、読み、感想を届けてくれました。
それを彼に転送しました。
「旧友の反応ありがとうございます。励みになります。緩和病棟が緩和されないので出てきました。酒飲んでもいい病棟でしたが病院で飲む酒の不味いこと。自宅ベッドで末期がん患者らしく横たわっています。まさか自分にこの境遇が来るとは、思いもよりませんでした。 中山 均」
それから10日後、彼の死の知らせを受け取りました。
作家として死にたい。それが彼の最後の望みだったのだと思います。
私も書き続けることを決意しました。
中山均君のご冥福をお祈りいたします。
了